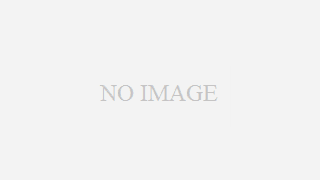 ふと考えること
ふと考えること 災害を「隠れ蓑」にするべからず(シャングリラ・ダイアログ)
そして、今時の震災に関して触れることは必要だし重要でしょう・・。しかしそこで終わりですか? アジアの日本への期待、つまり「地域の安全のために何が必要か」について何を語るのでしょうか? いつまでも震災を盾に世界情勢から目を背けていてはいけません!
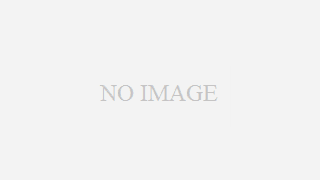 ふと考えること
ふと考えること 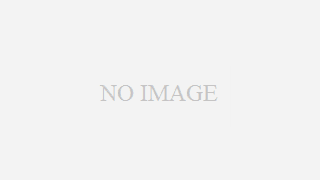 ふと考えること
ふと考えること 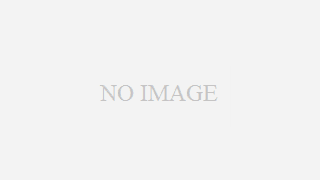 ふと考えること
ふと考えること 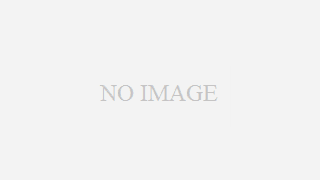 ふと考えること
ふと考えること 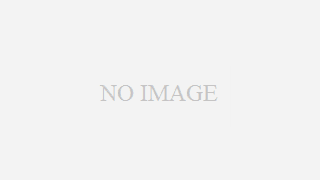 ふと考えること
ふと考えること 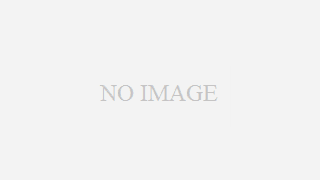 ふと考えること
ふと考えること 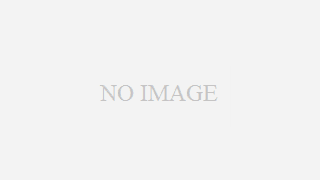 ふと考えること
ふと考えること 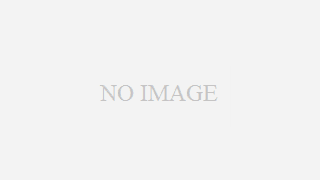 ふと考えること
ふと考えること 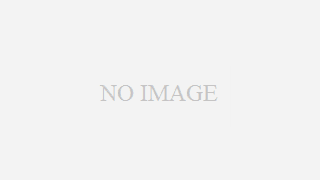 ふと考えること
ふと考えること 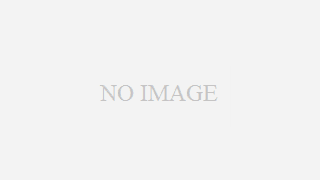 ふと考えること
ふと考えること